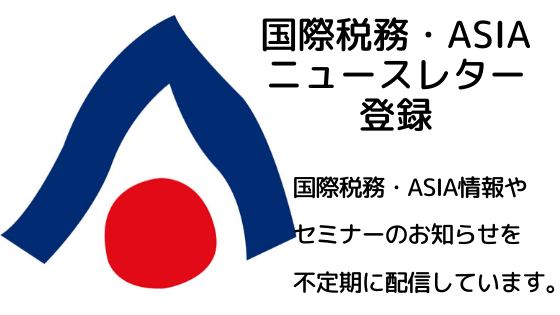LIBRARYライブラリー
CHINA 会計・税務 国・地域情報
【CHINA】中国撤退における清算と持分譲渡の比較について
2025.11.05
※ 本ブログはBUSINESS PARTNER株式会社BPアジアコンサルティング の原稿提供により掲載しております。
米中関税問題や中国自動車業界における急速なEV化などを受け、サプライチェーンの見直しが加速しています。これを受けて、中国拠点の整理を検討している企業グループも多くみられます。
中国拠点の整理の具体的方法には単独清算と第三者への持分譲渡が考えられます (注1)。ここで、単独清算は従業員解雇などハードな手続があることや、一部のコンサルティングファームでは持分譲渡を勧めるところもあり、持分譲渡による撤退を望まれる企業が見受けられます。
しかし、持分譲渡は清算に比べて決して容易・有利な手法ではなく、両者はその状況に応じて取捨選択すべきものです。
本書ではこれを解説して参ります。
注1:その他の方法に破産もありますが、外資企業に破産が適用されるケースは稀であり、またレピュテーションリスクもあるため、本書では割愛いたします。
まず、なぜ持分譲渡が好まれるのでしょうか。それは以下の理由が考えられます。
- 従業員解雇が不要である
- 結果、経済補償金を支払わなくてもよいため、コスト負担が発生しない
- 持分譲渡契約書を締結すれば撤退が完了するため、面倒な清算手続が不要である
確かにこのような側面もありますが、しかしこれらは一部の有利な点だけを「切り取った」幻想にすぎません。その理由は以下の通りです。
従業員解雇が不要である
確かに持分譲渡において解雇自体は不要ですが、オーナーチェンジにより従業員が身分や待遇の維持を要求することはよくあります。特に中国資本企業に譲渡する場合、外資企業社員でなくなることへの反発抵抗はよくあるケースの一つです。
とはいえ、従業員の解雇自体がないことは事実であり、やはり解雇がない持分譲渡に希望を持つ企業も一定数存在します。しかしこれは従業員解雇が相当大変である(例:一斉ストライキやデッドロック)というイメージを強くもちすぎている事の裏返しとも言えます。
巷には従業員解雇でトラブルになった事例はありますが、その発生割合や内容を鑑みず単に事例だけをもって「わが社でもトラブルになったらどうするのか」という考えに陥っては合理的な経営判断はできません。
トラブルになる例には、残業・手当の未払など会社に非があるもの、とりあえず抵抗して少しでも利益を勝ち取りたい一部特殊な従業員の存在によるものが考えられますが、これらは持分譲渡においても同様のトラブル・問題になりえます。
会社に非がある場合、買収予定者は法務調査をしてこれらの問題を発見する可能性は高いでしょうし、万一発見されなかったとしても、持分譲渡契約における保証条項でそのリスクカバーを要求してきます。
また特殊従業員はオーナーチェンジでも各種要求をしてくると思われ、持分譲渡が有利な手法であるとは言いきれません。
そして従業員解雇手続自体も、専門の弁護士等専門家のアドバイスに従って淡々と進めている事例のほうが大多数であり、合理的かつ冷静な判断をもって選択すればよいでしょう。
経済補償金を支払わなくてもよいため、コスト負担が発生しない
これは客観的視点に欠けた考えといえます。買収予定者から見れば、譲り受けた会社の社員が将来退職した際に、買収以前の勤務期間に相当する経済補償金(=過去勤務債務)も負担することになります。このため、買収価格から過去勤務債務に相当する額を引き下げるよう要請してくることが容易に想定できます。
もちろん、この過去勤務債務をいくらにするのか、また実際の解雇における経済補償金にはプラスαを積み増しすることも多く、両者には一定の差額があるかもしれません。しかし持分譲渡=経済補償金負担が一切ない、という考えは現実的ではないことを理解する必要があります。
以上の従業員解雇と経済補償金については下記の記事をご参照ください。
「中国駐在員に対する退職一時金問題について」 2025.07.11掲載
持分譲渡契約書を締結すれば撤退完了する為、面倒な清算手続が不要である
これは持分譲渡契約に至るまでの長い過程を無視した考えと言えます。
撤退の導入段階におけるハードルには、撤退を検討していることが社外漏洩しないようにする情報隔離問題もあります。そのような中何とか買収候補先を開拓できたとしても、その後法務・財務調査を受け入れ、多岐にわたる条件交渉を経てようやく持分譲渡契約に至ります。
清算においても導入段階の情報隔離、特に現地社員や取引先への漏洩防止には相当のハードルがありますが、重要かつ外部の第三者である買収予定者を探索し交渉することは更に難度が上がることを忘れてはいけません。
また清算は登記抹消手続が必要ですが、これは会社だけで判断・推進できるものです。一方持分譲渡は買収相手の同意が無ければ進められないものであることも忘れてはいけません。
以上、持分譲渡と清算を比較しましたが、持分譲渡が決して劣る方法というわけではなく、持分譲渡に過大な期待を持たず、全体を客観的に見て判断していただければ結構かと思います。
なお持分譲渡が選択されるケースには、中国現地法人が土地使用権を持っている場合が挙げられます。これは土地使用権があるから持分譲渡スキームを選択しているともいえるのですが、その詳細は下記の記事にて詳述していますのでご参考ください。
「中国の土地使用権譲渡スキームについて」 2025.06.10掲載
株式会社BPアジアコンサルティング(BP日本)・上海麦統商務諮詢有限公司(BP中国)では日本・中国の公認会計士、CPAからなる会計税務の専門コンサルティングファームとしてM&A・組織再編スキームの事前検討やその実行、会社清算の実務運営サポートなど一連のサービスを提供しています。ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
この記事について、中国進出のお問い合わせは CONTACT までどうぞ。